|
「宇宙から見た北海道の湿原」高田雅之さん(北海道環境科学研究センター)高層湿原と低層湿原
いっぽう、釧路湿原のほうは、歩こうと思っても非常にぬかるんで、全体が水びたしといった状態。はっきり違いがあるので、サロベツ原野のような湿原を「高層湿原」、釧路湿原のような湿原を「低層湿原」と、私たちは呼び分けています。 さて、そもそも湿原とは何でしょうか。ひとつ定義をご紹介すると、「地下水位が高い環境に成立した植物のまとまり。湿原は泥炭の上に成立することが多い」。何かだまされたみたいな気がします?(笑) 「泥炭」は、れっきとした土壌ではあるのですが、枯れた植物が低温のために分解が進まなくなってしまいます。それが堆積している状態のものを「泥炭」と呼んでいます。 その泥炭の上に生える植物もさまざまで、サロベツのような高層湿原では、ミズゴケが発達しています。あそこのミズゴケは、川水には頼らず、空から降ってくる雨と雪だけで涵養されている植生です。 かたや釧路湿原(低層湿原)の場合は、湿原の中を細かく枝分かれして流れている川が頻繁に氾濫して、その水によって涵養されたヨシが広く分布しているんです。その土地土地に地形や気象によって異なるタイプの湿原がそれぞれ発達しているのです。 湿原の生き物たち こんな湿原は生態系も独特です。どんな生き物が生息しているかというと、例えばイトウという魚は湿原環境を代表する種だと言えるでしょう。タンチョウ、シマアオジ、ノビタキといった鳥たちも湿原に暮らしています。アカモズのように、近年激減してしまった鳥もいますね。コモチカナヘビ、キタサンショウオ、トウキョウトガリネズミといった小動物も湿原の生き物です。 デンマークなどの北欧に発見例が多いのですが、湿原の泥炭の中からはヒトが発掘されることもあるんですよ。「Bog people」と呼ばれています。およそ2000年前の地層から、ほとんど分解されない姿で発見されたこともあります。もしかすると当時「生け贄」として湿原に沈められた人だったのかも知れません。 減少する日本の湿原 地球上では、泥炭は主に北半球の高緯度地帯に分布していますが、熱帯地方にも点在していて「熱帯泥炭」と呼ばれています。 日本列島にはかつておよそ20万ヘクタールの湿原がありました。しかしそれは明治・大正時代のことで、そのころに比べると、いまは湿原の面積は60%も減少しています。日本の湿原の8割方はここ北海道にあって、ざっと150カ所を数えますが、たとえば、ここ滝川もその中に含まれていた石狩大湿原は、かつて5万5000ヘクタールを誇っていたのに、現在では200ヘクタールにまで縮小しています。サロベツ湿原もこの100年で半分の面積になりました。湿原は開発されて主に農地になり、わたしたちの食料生産を支えてくれているわけですが、引き替えに湿原環境は失われてしまいました。現在まで残った湿原も、保護区に指定されているのはおよそ半分に過ぎません。特に小さな規模の湿原は保護されていないというのが現状です。 泥炭の利用 北海道の湿原は泥炭の上に発達していることが特徴ですが、人間は古くから泥炭を利用してきました。泥炭はいったん火がつくとなかなか消えません。地中で延々とくすぶり続ける「泥炭火災」はやっかいな自然災害です。そんな泥炭はかつては燃料としての利用が中心でしたが、近年ではオイルフェンスの材料、土壌改良材、園芸用資材として利用されるようになっています。 サロベツ湿原を高空から撮影すると、泥炭の採掘後が筋状に残っているのがよく分かります。これは戦争中、泥炭を防毒マスクの材料に使えるのではないかという目的で採掘されたようです。この場所は現在は掘り跡のほうが湿原状態として残り、皮肉なことに泥炭が採掘されなかった場所ではササが入り込んでしまっています。 火山と湿原 いっけん結びつきはなさそうに思えますが、火山の「爆裂火口」(爆発によって生じたクレーター状の盆地地形)に、のちのち湿原が発達するケースは少なくありません。日本海に浮かぶ利尻島、ここは利尻岳を擁する火山島です。その利尻岳の南側の裾野にある「沼浦湿原」と「南浜湿原」は、爆裂火口跡に出来た湿原だと考えられています。 いっぽう西海岸にある「種富湿原」は、同じ火山の影響でも、噴火時にできた溶岩流のくぼみに水が溜まって発達したタイプの湿原です。 この南浜湿原で、わたしは6メートルのボーリング調査をしたことがあります。ここでは泥炭の厚みは一年に1ミリほどしか増えていないことが分かりました。50センチの泥炭が出来るのに500年かかっているということです。長年にわたる営みが湿原をかたちづくっているのです。 リモートセンシング ALOS(エイロス)という名前をご存じでしょうか。日本産の「HII-A」ロケットで打ち上げた陸域観測技術衛星の名前で、愛称を「だいち」といいます。 参考 宇宙航空研究開発機構 こんなふうに、遠く離れたところから対象に直接触れずに観測し続けることを「リモートセンシング」と呼んでいます。これがわたしの研究分野で、このような空中写真や衛星画像を元にしたGIS(地理情報システム)を活用して「湿原を読み解く」ことが目標です。 大切な「現地情報」 とはいえ、衛星画像から全てが分かるわけではありません。むしろ現地調査の結果と衛星画像を付き合わせて、誤差を最小化しながら分析を進めるという手順が欠かせません。何よりフィールド情報が大事なのです。 具体的には、まず湿原に出かけていって、できるだけ綿密に現地調査をやります。たとえば植生を調べ、地図上にデータをプロットしていきます。ただし、広大な湿原全体をくまなく歩くことは不可能なので、データは地図上に点状に落とすことになります。 次に、ALOSの衛星画像をこの地図に重ね合わせます。そうして画像情報に、実際に調べた植生データを対応させていきます。なかなか難しい作業なのですが、この突き合わせがうまくいくと、画像情報だけからでも任意の場所の植生を推定することが出来るようになります。ここまでくれば、あとは2週間ごとに撮影されるALOS画像を追っていけば、この間の植生の変化なども追跡できるようになるのです。 ですから「リモセン」「GIS」などと言っても、実際はわれわれは現場の仕事が多いわけですけれど、うまくやると衛星画像からその湿原の植生はもちろん、土壌水分とかササの生えている高さとかまで分かるようになります。 雪解けラインを追いかける渡り鳥 そのいくつかの成果をご紹介しましょう。 湿原の泥炭というのは、その名の通り多くの炭素を含んでいます。さきほどご紹介した利尻島の種富湿原で、わたしたちは、現場で調べた実測値とGISの技術を使って、この湿原の泥炭の炭素含有量を推定してみました。すると、面積1.8ヘクタールのこの湿原には、913.9トンもの炭素(C)が蓄積されていることが分かりました。 参考 ここ滝川を含む空知地方の石狩川流域には、かつて石狩大湿原が発達していて、いまも宮島沼、親子沼、うりゅう沼、丸沼、茶志内沼といった小さな沼が点在しています。「河跡湖沼群」といって、蛇行していた川が氾濫のたびに川筋を変え、元の川筋に沼を残していくのです。 この湖沼群は南北130キロに及んでいますが、ここがハクチョウやガンなどの渡り鳥たちの重要な居留地になっていることは皆さん、よくご存じでしょう。 そこでわたしたちの研究グループは、アメリカのTerra/Aqua(MODIS)という衛星の画像を元に、この地方の春の雪解けと水鳥の移動の関係を調べてみました。 ALOSが2週間ごとだったのに対し、MODISは毎日1回ずつ同じ地点の写真を撮影してくれるので、南の方からだんだん沼の氷が開いてくる「融雪ライン」を日を追って追跡できます。すると、この地方の「融雪ライン」はだいたい1日に2キロから2.4キロのスピードで北上していく、ということが分かりました。 いっぽう、地上では渡り鳥たちを追跡し続けました。その結果、マガンたちの移動スピードは1日当たり1.89キロから2.25キロ。ハクチョウもほぼ同じです。衛星で調べた「融雪ライン」のスピードと見事に一致したのです。 こうして、マガンやハクチョウたちは春の渡り時期、地上の融雪ラインを追いかけるように北帰行を続けているのだということを明らかにすることが出来ました。 こうした例からも分かるように、われわれの仕事はパソコンとニラメッコばかりしていてもダメで、80%は実際のフィールドに出かけて現地調査をしています。つまり、正確なフィールド情報があって初めて、人工衛星の画像が生きてくるのです。 これできょうのお話はお終いです。ありがとうございました。 たかだ・まさゆきさん 1981年、宇都宮大学工学部環境化学科卒業。民間企業を経て1983年に北海道庁入庁。以後、環境行政に携わり、その間1993年に環境庁自然保護局、1999年に国立環境研究所に出向。2002年から北海道環境科学研究センター環境GIS科長。専門分野は湿原、GIS(地理情報システム)、リモートセンシング、環境情報など。近著に『北海道の湿原』(北海道新聞社、共著)がある。 |
|
2007年6月23日、たきかわ環境フォーラム「エコカフェ」(滝川市森のかがく活動センター)での話題提供から。(C)Masayuki Takada, All rights reserved. |
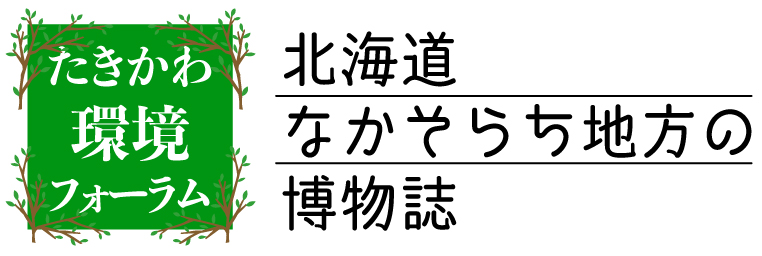
 サロベツ原野と釧路湿原。北海道を代表する2つの湿原と言っていいと思いますけれど、同じ湿原とはいえ、よくみるとかなり違う性質の湿原であることが分かります。サロベツ湿原は、ミズゴケの上を歩くと、フワフワ柔らかくて、まるで布団を踏んで歩いているような感覚です。
サロベツ原野と釧路湿原。北海道を代表する2つの湿原と言っていいと思いますけれど、同じ湿原とはいえ、よくみるとかなり違う性質の湿原であることが分かります。サロベツ湿原は、ミズゴケの上を歩くと、フワフワ柔らかくて、まるで布団を踏んで歩いているような感覚です。