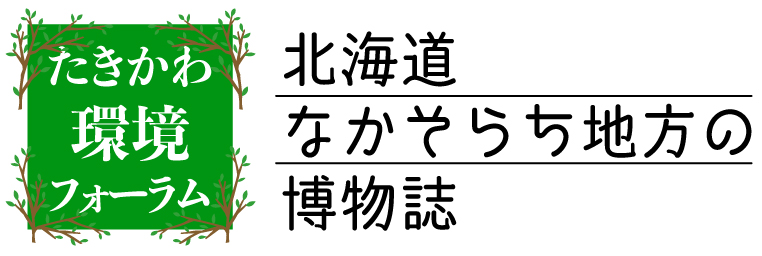|
白い花、真赤な実……りんご園のある風景
伊藤規子さん(りんご生産農家)
ご存じのように、日本の農家はいま、高齢化と人口減少がずいぶん進んでいます。滝川市内を見ても、2000年に788戸あった農家が、いまでは543戸。この10年で3割ほども減りました。
輪をかけて減っているのが、りんご農家です。江部乙出身の岩橋英遠画伯(1903-1999)が残した故郷の風景画作品には、あちこちにりんご園が描かれていますけれど、今では「りんご園なんてどこにあるの?」と聞かれるほどの数になってしまいました。
正確には、それでも20軒ほどはあるのですが、少ないおかげで逆に結束は強くなっていて、お互いのりんご園を見学しあって、勉強会なども開いています。
中には50年選手のりんご生産者も少なくありません。対する私は、札幌から30歳で滝川にやってきて、農業を始めたのは35歳の時。わずか10年ほどの経験しかありません。ベテランをさしおいて栽培のお話しはとてもできませんけれど、きょうは「りんご農家の広報係」として、みなさんにりんご栽培の魅力をお伝えしたいと思います。
4回以上、素手で触る
さてみなさん、お米や野菜を作っている田畑と、りんご園の違いはなんだと思います? 実は決定的な違いがいくつかあるんです。
まず、田んぼや畑なら、作付けるのは1度に1品種ですよね。「ななつぼし」と「きらら397」を混ぜては植えないし、「ハルユタカ」と「ちほく」を一緒には育てません。混ぜたらブランドが付きませんし、栽培中も、株によって成長スピードが異なったりすると効率が悪くて仕方ありません。農業機械も使いづらいだけです。
ところがりんごの場合は、1品種だけ並べて植えていたのでは、実が生らないんです。例えば、「つがる」の花には、「つがる」とは違う別品種のりんごの花粉を授精しないと結果しません。
機械化に全く向かないのも、りんご園の特徴といえます。というか、収穫物の1個1個にこんなに素手で触る農業も珍しいと思います。「実すぐり」「葉摘み」「袋掛け」「収穫」と、最低4回は触ります。
レイチェル・カーソンという生物学者が書いた『沈黙の春』(1962年)という本がとても好きなんですが、その冒頭に、現代の農業は自然の理に反している、という意味のことが書いてあります。1品種しか生えていないなんて自然界ではあり得ません。農薬や機械力に頼らざるを得ない畑作農法は、確かに自然の理に土台から背いているのかもしれません。
その点、りんご園の農業法は、比較的自然に近いと言えます。機械は使えない、収穫までに最低でも5年はかかる――。「何でそんな効率の悪い農業を続けているの?」と聞かれたことがあります。でも私は、だからこそりんご園に執着したいと思っています(笑)。1個1個に何度も手を触れて収穫したりんごが、私には自分の「作品」だと思えるのです。
リンゴ園の12カ月
 |
 撮影/伊藤規子 |
 |
さあ、滝川のりんご園の1年をスライドショウでご覧いただきましょう。
まだ雪の厚い2月、りんごの木の剪定作業が始まります。うちのりんご園では、若木から15年生の木まであって、バランスを見ながら少しずつ更新しています。
4月になると、地面に落としておいた枝拾いをして、本格作業の準備です。1本1本の根本に施肥したり、畑を起こして苗木を植えるのもこの季節です。
やがてりんごの木は一斉に花を付けますが、白い中にほんのりピンクがまじったようで、本当にきれい。真っ赤な花を咲かせる木もあって、これはメイポールという、りんごの原種に近い品種ですね。酸っぱくて食用に向きませんが、うちではこのメイポールを花粉交配用に育てています。
夏を迎えるころにはどんどんりんごの実が育ってくるので、収穫する実だけを残して後はもぎとってしまう「実すぐり」をします。
さ~て、ここで問題です(笑)。用意しましたのは、「実すぐり」をする前の一振りの枝。だいたい150個のりんごの小さな実がついています。プロが「実すぐり」をしたら、いったいこのうち何個のりんごが残るでしょうか?
では実際にやってみますね。(プチプチと猛スピードで小さな実をもいでいく)
ポイントがいくつかあるんです。りんごの実に栄養を送っているのは、光合成をする葉っぱですが、「りんご1個に36枚の葉っぱが必要だ」と言われているんですね。りんごの花は1カ所に5輪ずつ咲きますから、まずそれを1個ずつにします。次に、去年や今年になって伸びた新しい枝には、良い実が付きませんので、これももぎ取ります。3年目以上の枝に、おいしいりんごが生るんです。
さあ、こんなところでしょうか。クイズの答えは……19個でした!
続く作業は「袋掛け」。防虫のためと見られがちですが、それだけではありません。涼しい日にぱっと袋を外して日光を当てると、実がきれいに色づくのです。
また「葉摘み」は、りんごの実に葉っぱの影が映り込まないよう、実のそばの葉を1枚ずつ取り除く作業です。これを怠ると、実の表面に葉っぱの影の跡が残って、見映えが悪くなったりします。
リンゴ作りは「対面栽培」
私にりんご栽培を教えて下さっている師匠がいるのですが、私があんまりしつこく質問すると、「そんなことはりんごに聞け!」と言われてしまうことがあります。でも確かにそうだと思えることも多くて、りんごって「対面栽培」で作るもの、と言えるかも知れません。
こんなふうなりんご栽培って、何かに似ていると思いませんか? そう、子育てとそっくりなんです。りんごにはいろんな品種がありますが、みんな個性的で、それぞれいいところもあれば、欠点もあります。作り方に決まったマニュアルがないのも、子育てと同じ。作る人が毎日りんご園を回って、文字通りりんごたちに声をかけながら、じっくり育て上げているんです。
お店で売られているのは、そんなふうにして育てたりんごの中でも、エリート中のエリートたちだけ――このことを消費者のみなさんに知ってもらえるだけでも、生産者としてはうれしいと思います。
きょうのお話はこれでおしまいです。どうぞみなさん、気軽にりんご園を訪ねてきてください! ありがとうございました。
|
りんご(食用)の主な品種旭(マッキントッシュ・レッド)、つがる、スターキング、あいかの香り、あかね、紅将軍、マオイ、、昴林、ノースクイーン、王林、ハックナイン、さんさ、レッドゴールド、ヒメカミ、紅玉、北斗、きたろう、ふじ、ジョナゴールド、ビスタ・ベラ、きたかみ |
2009年8月29日、たきかわ環境フォーラム「エコカフェ」(滝川市森のかがく活動センター)での話題提供から。(C) Noriko Ito, All rights reserved.
報道機関向け資料(pdf、85KB)
エコカフェ2009リーフレット(pdf、619KB)