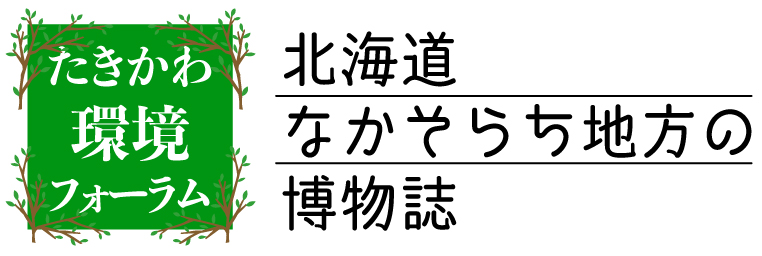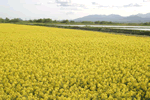|
なばな王国…その歩みと菜の花パワー
中野義治さん(菜種生産農家)
聞き手 伊藤規子さん(たきかわ環境フォーラム)
伊藤さん
中野さんは20年ほど前から、滝川市内で最初に食用のなばな(菜花)の生産に取り組まれてきた方です。今ではなばなは、春一番に採れる野菜として、滝川の特産品のひとつになりました。菜種油も自分で作っておられます。まずは菜の花の基本から教えて下さい。
中野さん
じつは「ナノハナ」という名前の作物はないんです。私たち生産者は、春一番の野菜としてそのまま食べるのを「なばな」、種から油を搾るほうを「菜種」、と使い分けています。
油を搾るための菜種は、滝川でも過去に作付けされていたことがあります。私は昭和63年から始めて、平成元年に最初の花を咲かせました。農産品としてだけでなく、きれいな菜の花畑の景観を滝川の観光の目玉にできないだろうか、とも考えました。平成11年に農協が合併したこともあって規模拡大が進み、私の畑だけで現在の作付面積は約30haにまで増えました。滝川全体では約200haで作付けされています。
私は、なばなを春一番に収穫できる野菜として出荷したくて、研究の進んでいる独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の「東北農業研究センター」(岩手県盛岡市)まで出かけて勉強し、自分でも生産を始めました。みなさんに親しんでもらっている「雪割りなばな」ですが、じつは私が勝手にネーミングしたんです(笑)。販売も農協を通さず、自分で売り先を開拓しました。
菜種のほうも搾油まで自分でやっています。名前は「育てて搾った中野の気持ち」。275g入りで1ボトル840円です。
この値段、植物オイルにしては高い、と感じられるかも知れません。でも、品質のための労力を惜しんではいません。自分で販路を開拓していくうち、消費者の中にも「本物の味の分かる人」はいる、ということを実感しました。大量生産のサラダ油などは、遺伝子組み替え作物を原料にして、酸化防止処理もされています。でも私の油は違います。畑の土壌作りから品種選びまでこだわり尽くし、搾油まですべて手作業で、添加物もゼロです。
私の菜種油でしたら、後はレモンと塩を加えるだけでおいしいサラダ・ドレッシングができます。目玉焼きやチャーハンを作ってもらったら、味の違いがお分かりいただけるはず。揚げ物に使うにはもったいないですけど(笑)。ただ、添加物なしで酸化しやすいので、必ず冷蔵庫で保管してもらっています。
「育てて搾った中野の気持ち」は、年間1500本ほど作っていますが、毎年作付場所が変わるので、年によって油の味に違いがあるのが分かります。
滝川では、菜種の種まきは8月中旬。翌春に花が咲き、7月下旬から8月上旬にかけて収穫します。菜種は連作(同じ圃場で何シーズンも続けて栽培すること)すると病気が出やすいので、収穫した後の畑には麦や大豆を作付けして休ませます。
 菜種搾油機の操作を実演する中野義治さん(左) |
|||||||||
|
伊藤さん
中野さんが作っているような良い油が、なぜもっと広がらないのでしょう?
中野さん
まず、なばなに関しては、出荷期間が短い、というのは宿命かも知れません。現在、滝川なばな生産組合には組合員が35名います。なばなブランドを確立して、例えばスイーツに使ったり、冷凍保存を試してみたり、いろいろ使い方を考えているところです。
なばな/菜種の魅力は、本当にたくさんあると思うのです。
油は単品で売るほか、揚げたり炒めたりの料理や加工食品に使っても販路があるでしょう。石鹸やロウソクの原料になりますし、そのロウで家具製品を磨くのもいい。菜の花畑ではちみつを採ればこれも滝川産です。
油の搾りかすは家畜の飼料になりますし、劣化した食用油はいま、BDF(バイオディーゼル燃料)として市内のゴミ収集車の燃料代わりに使われています。
菜種油を燃やしてススを集めたら墨だって作れるでしょう。真冬のイベント「ランタンフェスティバル」のロウソクをすべて滝川産菜種で作る、というアイディアなんか、どうでしょうか。
菜の花の花言葉は「快活」だそうです。黄色は人を幸せにする(笑)。「菜の花まつり」の開催で、全国の生産者や消費者との交流も大きく広がっています。
私は、この地域には菜種がとてもよく合っていると思うんです。雪が多くて地表がしばれにくいので、越冬するのに好都合ですし。
わが家ではファームインといって、都市部の消費者や若者たちに農場体験をしてもらっています。大学と連携して、学生さんたちも大勢訪れています。菜の花をひとつのキーワードに、産業・観光・交流など、色々な面で展開が広がればと思っています。
2009年6月27日、たきかわ環境フォーラム「エコカフェ」(滝川市森のかがく活動センター)での話題提供から。
報道機関向け資料(pdf、93KB)